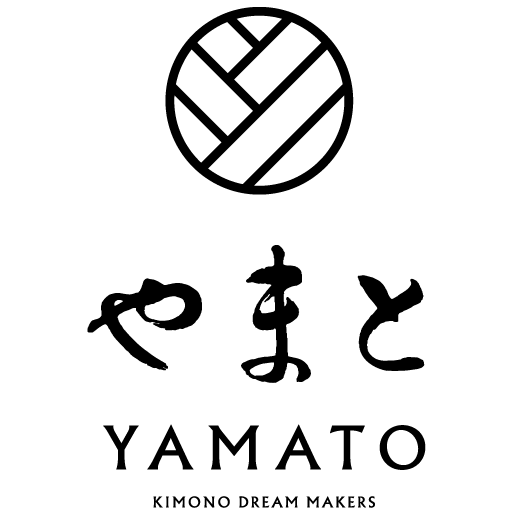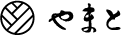グローバル社会における日本のものづくり
中村信喬氏×矢嶋孝敏

グローバル社会について
矢嶋:「グローバル社会」という言葉ですが、今月の「文藝春秋」に200万部の大ベストセラー「置かれた場所で咲きなさい」の渡辺和子さんがこのようなことを書かれていました。「最近流行のグローバルという言葉が嫌いです。…日本人らしさを取り戻して欲しい」と。グローバルという言葉を広辞苑で調べると、「世界的な・地球規模の」とあります。グローバルを解釈すると渡辺和子さんがおっしゃるようにグローバルは嫌いで日本人らしさが良いとなるのです。何故でしょうか。グローバル=世界的な基準は、言い変えれば“文明的な基準”となります。文明というのは世界共通なものです。飛行機は典型的な文明と言えます。国によって飛行機の構造が違うなら危なくて乗っていられません。食べるもので典型的な文明を挙げれば日本人の大発明と言われるカップヌードル。なぜカップヌードルが文明かと言うと、沸騰したお湯を3分間入れれば誰が作っても同じ味になるからです。そういう世界的な規模の、誰がやっても同じような結果が出るというものがグローバルという意味だと私は思います。今、地球がどんどん狭くなっていっていることも事実です。今日も朝起きればアメリカ大統領選挙の速報がすぐ見られる訳ですから。しかしそのように文明的に世界が近くなればなるほど、今度は文化というものが大事になってくるのではないかと私は思います。

矢嶋: 皆さん京都の“伏見稲荷”はご存知ですよね。朱い千本鳥居が下から上まであって日本人にも中国人にも非常に人気です。ところが日本の観光客は千本鳥居の入り口で写真を撮って帰ってきてしまう。逆に中国人の観光客はその千本鳥居を通り抜け、更に1時間くらいかかる奥の院まで行ってお参りし帰ってくる。
日本人にとって文化は “いつも在る”ものなのです。ところが中国人にとって文化というのは“無い”んです。4000年の歴史がある中国であっても文化大革命で本土の主なものは無くなっていますし、故宮博物院の中身は蒋介石が台湾に持って行きました。文化が現在あまりなくなった中国の人が日本の文化に興味を持ち伏見稲荷奥の院まで行くことになります。一方、日本人は文化がいつも在ると思っている。“いつまでも在ると思うな親とカネ”という言い方をしますが、私はそれに“いつまでも在ると思うな親とカネと文化”と言いたいのです。グローバルという規模で文明がどんどん進めば進むほど、ローカルということの価値が上がってくる。グローバル社会において意味のあるものはローカル文化であるという、逆説的かつバランスの取れている論理が成り立ちます。
「そうだ 京都、行こう。」というJRのコマーシャルがあります。これは新幹線という文明に乗って京都という文化にわざわざ会いに行くということです。また旅行代理店の広告でも「エールフランスに乗っていくカッパドキアの旅」というのがありました。カッパドキアという文化に会う為に、飛行機という文明を使って行く。それは“グローバルな社会になったからこそ出来るローカルの享受”“ローカルを味わうコト”なんですね。そういう意味ではグローバル社会だからこそローカルの見直しが進んで行くし、文明社会だからこそ文化を求めるようになってくる。グローバルという言葉が語られるときにいつもそれに対してローカル、あるいは文明が語られるときにいつも文化というものを対峙して考えるとわかりやすいのではないかと思います。これは対立した概念ではありません。文明の価値観というのは「安くて早くて便利なもの」。これはモノに対する価値観です。それに対し文化の価値観は「安くなくても良い、早くなくても良い、便利でなくても良い」、つまり心に対する価値観なのです。
カップヌードルは文明ですが、文化は“お茶”だと思います。今朝、承天寺に行きご住職にお茶を入れてもらいました。美味しかったです。お茶はいれる人によって明らかに味が違います。今日の温度・湿度を考え、どれくらいの温度にするのか、湯冷ましにいれ塩梅を見る、蒸しの時間も異なる、勿論、茶葉によっても違ってくる。それを見計らうという“面倒”なことをして出てくるのがお茶です。
シャワーも典型的なグローバルと言えます。どの国に行ってもシャワーは同じ機能です。一方、温泉はとてもローカルなものです。湯布院の温泉と別府の温泉と黒川温泉とでは同じ九州でも違います。
このようにグローバルになればなるほどローカルという価値が上がってくる、というのが私の考えです。
中村:昨年、東京芸術大学で「グローバルとローカル」について講義をしました。同大学では、技術は高いが一歩社会に出たとき、どこかアーティスト気分で社会と上手く連携できないという課題を抱えており、実際に社会でやっている人に話をして欲しいという依頼でした。
グローバルというと「グローバルの中に出て行く」「グローバルに合わせに行く」とよく捉えられますが、そのように“合わせにいこう”とすることで、もともと日本人の凄いものがあったにも関わらず、明治期から日本の工芸美術が下に置かれるようになってしまっています。同様に東京芸術大学でも、地方から出てきた学生さんが東京の分厚いアートの世界の中で戦うと、皆同じように東京ナイズされて一般化されオリジナリティーを失っていくことがあります。そこで、一度自分の故郷に帰ってごらん、という話をしました。故郷にはお祭りや、その土地の食べ物があったり、生活があったり… つまり、そこに帰るとその人しか知らないことがあるのです。それを東京に出てきた洒落たセンスと融合すれば、オリジナリティーが生まれ、抜きん出ていきやすいわけです。「ローカルの方に逆に世界を引きつけてグローバル化してしまう」ということです。
日本の工芸美術は今、再評価されています。向こうが知りたがり、そして、見たがっています。外国の富裕層などは日本のことを良く知っています。先ほどの伏見稲荷もそうですし、沢山の方が日本を訪れます。だからこそ自分たちのローカルなものをセンス良く発信し引き寄せることで、向こうから来させる感覚が必要だと思います。グローバルの中で日本のものを引っ張りだし合わせるのではなく、日本のローカルなものにグローバルな世界のステージを合わせてしまうということです。
さて、私は“人形で人形は勉強できない”と良く言っています。人形は人の形ですから、きものを着ていたり、色々な主人公がいたり、どんな場面・シチュエーションで、何をしているか というモノを作っていくわけですが、そこでは、ただ単に人形を作っていては駄目です。サッカーの岡田監督がイタリアに監督の資格を取りに行った際、イタリア人から「岡田は何をしに来たのか?」と言われ「サッカーの勉強に来ました」と言ったところ、その方より「だから駄目なんだ、折角イタリアに来ているのに、オペラや美術館等を何故見ないのか」と言われたそうです。監督というのは人を動かす仕事、そういうものを見ずして人の何が分かるのか、ということでした。サッカーだけを勉強しても駄目なのです。
同様に帯を作る人は織物として帯を学んでも、帯だけ見ていては帯のことは勉強できないと言えます。自分の足下、周辺環境を見ず上辺ばかり勉強している若い人は多いですが、この「ローカル」を客観的に見つめることが、グローバルに飛び出して行ったときに「オリジナリティー」となり、人が感銘を受けるものになるのだと思います。私は今「やっぱり博多にいて良かった」と思います。“ここにいるからこそ強い”という気持ちが年々高まっています。自分の持つ強さは何か?と問うたとき、やはり人の形を作っていく、そして代々続いている、それは誰にも負けない、それが私の武器です。
先週、日本伝統工芸展が開催されましたが、人形=「ドール」という表現を東京展ではしています。福岡会場では「NINGYO」というローマ字に4~5年前からしました。漆も以前は「ラッカー」、もっと前は「ジャパン」と言われていましたが、今は「URUSHI WORK」と英語に置き換えるようになりました。人形は酷いときは「Toy」=玩具と言われます。私たちはこれからローカルからグローバルへ発信する際、英語を覚え、相手に説明することが必要です。人形をローマ字で「NINGYO」としたとき、向こうの人たちは置き換える言葉がないので「NINGYO」って何?と聞いてきます。そのとき自分たちがどのように伝えるか。スカルプチャーなのかフィギュアなのか、色々な言い方をして向こうの方にわかってもらいます。モノを見てもらえばわかるはずです。そのモノが、やっぱりどこにもないもの、誰もしていないことには感動を覚えるだろうし、逆に駄目だね、と思われるかもしれない。これが私の思うグローバルであり、尚且つローカルをどうやってグローバルにさせていくかということだと考えます。
グローバル社会について
矢嶋:今の信喬さんの話で「博多に生まれて良かった」というのが良くわかります。私は新宿生まれですが、日本に生まれて良かったと思います。
1976年、26歳のとき私はアメリカに行きました。建国200年祭でした。そんな中、米国の友人たちが、矢嶋がわざわざ日本から来たのに恥ずかしい…というのです。見せるものが3つしか無いと。1つはフィラデルフィアの自由の鐘、もう一つはジェファーソンの独立宣言、そして自由の女神だと。でも200年でこの国を作ったじゃないか、ジャズという文化もアメリカで生まれた、ということを友人に話したことを今思い出しました。博多も日本も「文化がある場所への感謝」をしながら、その文化をもっと深める学習をせずグローバルという言葉に流されてはいけない、という意味で信喬さんが先ほどお話されたのだと思います。
さて、「ものづくり」という言葉で一番印象に残っているのは、信喬さんから聞いたのですが、「モノを創れる者は神に選ばれし者なり」というミケランジェロの言葉です。これにはすごく深い意味があると思うのです。ここにボールペンがありますが、このボールペンが壊れたら直すことが出来ず捨ててしまいます。ボールペン1つ作れない。「モノをつくることの価値、或いは大切さということをもっと知る必要がある」ということです。使い捨ての文明の中でモノの価値というのは非常に見えにくい。100円ショップはとても便利だけど100円ショップで買ったものを大事に使った…という気はしません。ものづくりとは「モノをつくることに対する敬意」と「つくられたものを大切にする心」だと思います。その中で一番言えることは“直して使う”ということです。これは父親の形見の時計なので3回くらい直していますが、直すのは何万円もかかります。そのモノをすごく愛し、これからも使おうとするから直しに出すのです。これがとても大事なのです。きものはこの10年間で直しが5倍に増えています。新しいものを買うのではなく、父親・母親のきもの、祖母のきもの、叔母のきもの等を直して着るということは、とても素晴らしいことです。洋服の場合、そこまで直して着るという文化はありません。「直して着る」とは、その作られたものを大事にするという気持ちです。これがものづくりの根源ではないかと思います。皆さんの中で今まで病気や怪我をしたことがないという方はいませんよね。ということは多かれ少なかれ自分の身体を直して生きているのです。私も自分の身体をいろいろ修繕し、あるいは整えることによって今日みなさんにお目にかかれているのです。ものを大切にする心があれば、簡単に人を殺したり動物を殺したりしない筈です。モノをつくるということは、自分も、他人も、あるいは動植物をも大事にしていく心につながると思います。
ものづくりというのは元々「自給自足」でした。自分で食べる食物をつくる、あるいは自分で土を焼いて食器をつくっていたのがだんだん変化し「地域分業」になってきました。焼き物だったら有田が良い、信楽が良いなど。そうなると次は、土を探してくる人、焼く人、釉薬をつくる人というように「仕事の分業」となります。最終的には「モノをつくる人とモノを使う人の分業」になってきます。昔は自分でつくり自分で使っていました。今はモノを創る人と、モノを使う人が分かれています。ですからモノを創る人は、自分が創りたいものを創るという根源的な気持ちと、相手の役に立つ、民芸運動で言えば相手の「用に立つ」モノを創るという2つの軸を求められます。それを混同してはいけない。自分で創りたいものがあって良いのです。同時に、どういうものを自分が創るかを良く考えないと、創りたいものでもなく、用に立つものでもない、非常に中途半端なものができてしまう可能性があるのです。
それは商品としては流通しません。創られた製品と、それ自体が金銭的価値を持つ商品とは違うのです。ですから「製品を創るか、商品を創るか」ということは、ものづくりの大きな分岐点なのです。商品とは、それ自体が他の人から認められる価値をもっているものです。尚且つその価値は抽象的なものではなく具体的なものです。何故ならば「値段」がつけられるからです。作品には値段がつきません。自分の子供が幼稚園のときに作った粘土細工で父親の顔を創ってくれたとすれば、どんな下手なものでも取っておく訳です。それは心のこもった作品かもしれないけど商品ではありません。だからモノをつくるという時、自分はどっちを創りたいのか、ということを考えていかないと、創る人と使う人が分かれた世の中ではどっちつかずで中途半端なものになってしまいます。
中村:矢嶋会長のミケランジェロの言葉は、私が大学生の時に読んだ本にありました。この「もの作りは神に選ばれし者」という言葉を、博多織デベロップメントカレッジの入学式では必ず言います。神から選ばれた、と学生に言うと、僕は神様から選ばれたんだ、と舞い上がってしまうのですが、そんな筈はありません。神様から選ばれる人なんて、そんなに沢山いるはずはないのです。その後、私が感動したミケランジェロの行動がありました。大理石をずっと彫りつづけ、ようやく女神像の最後の仕上げというときにポンと鑿を入れたら欠けてしまったそうです。ミケランジェロは「本物が出てきた!」といって、ひと回り小さく彫って仕上げたそうです。壊れたり、何かがおこるということは、何かの力によって起きているということを受け止められる人だったのですね。
ものづくりという言葉ですが、よく父が「俺たちはものづくりだから」と言っていました。人形師、人形づくりとは言いませんでした。だから人形に限らず色々なものを作っていた人でした。もの作りとは、ものを作り出す人だと自分で言うのか、それとも、人から言われるのかでは大きな違いがあると思います。自分から発信したものと、人が評価するものとでは全く違うと思うのです。往々にして、自分たちは物を作っているから、という意識で学生が「これ凄いでしょ」などと言うことがありますが、「それがどうしたの?」と、私は言います。なぜなら誰のために創ったのか、何を想って創ったのかというのが大事だからです。

我が家には代々の家訓があります。祖父が残した家訓で「お粥食ってでも良いもの作れ」というものです。今でもこれがうちの中心になっています。何を作れとか、どういう技術、どういう材料で作れというのは全くありません。ただ単に「お粥食ってでも良いもの作れ」と。その“良いもの”というのは自分から見た良いものではありません。我が家は曽祖父の代に久留米の有馬藩の私塾とお茶道具屋から出て来て、米などの相場をやっており決して貧しい家ではありませんでした。そのような中で育った祖父が「お粥食ってでも」と。よっぽど貧しいか、病人かしか食べない時代にお粥を食ってでも…と言った祖父、そんな生活もしてないのになんでこんなことを言ったのだろう?と子供の頃から思っていました。父の代からもずっとこの言葉を受け継いでいます。
博多人形界は江戸、明治、大正、昭和とずっと続いていますが、戦後には何でも売れた時代がありました。歌舞伎もの・能もの・美人ものをつくったり、黒田武士などをつくれば売れていました。「こういうものをつくれば売れる」というマニュアル化されたものに乗ってしまったので売れなくなってしまいました。今ここにいる多くの方は全く博多人形を欲しいと思わないだろう…と思います。そういうことに陥ってしまっているのです。根本である“何のために”とか“どういう使命感をおびて創るのか”ということがなくなってしまったのだと思うのです。
以前、九州沖縄地区の工芸展の記念展に人間国宝の森口邦彦先生をお呼びし講演頂いたとき、先生が「ものづくりには必ず使命感が必要だ」とおっしゃいました。色々な作家が、様々な人や土地、生活に対し関わっていく中で、何か使命感を持って作品や商品を生み出すことが大事ということなのです。ただ自分がつくりたいものをつくるのとは違います。使命感というのは非常に大事だと私は思います。その使命感に基づき、祖父は人の形というものを何故つくり続けていくのかということを考えつつ家訓「お粥食ってでも良いもの創れ」と言ったのだと思います。
ものづくりというのは「何か目に見えない」ものであり、「技術や色をこう調合するという目に見えるもの」ではないと私は思います。それを息子に伝えようとしていますが、これはなかなか難しいことです。色々な言葉でも伝えきれません。目に見えないものですから。その目に見えないものを受け渡す。そうすればおそらく、人が感動したり、人形を見て涙を流したり、これをそばに置いておきたいといったモノを生み出せるのではないかと思います。ものづくりの中心にあるもの、それを我が家は代々大事にしています。
日本のものづくりについて
矢嶋: 小林秀雄さんの言葉に、こういうのがあります。「花が美しいのではない。美しい花がある」。これと同じです。花とは何か、日本とは何かという前に「様々な日本のローカルな文化があり、その集積されたものが日本だ」というように考えて良いと思います。その中から日本なるものが感じられれば良い。そうでないと、無理に日本らしきものを切り取ってこようとするとおかしなことになるのではないでしょうか。

矢嶋: 私は福岡空港についたときに、嬉しく思うのと同時に多少違和感を感じることがあります。空港の仕切りに博多織の柄、一本独鈷があります。ホテルのカーペットやスリッパの袋にも博多織の柄が用いられています。しかしこれは博多織ではなく、博多織のデザインなのです。それを私は否定しているわけではありません。
もう一例挙げます。京都の老舗メーカーの中には、ものづくりをやめて何百年続いたデザインを海外に売る会社が増え始めました。それは1つのビジネスです。しかし自分たちのコンテンツを売って利益が出るかも知れませんが、果たしてものづくりと言えるでしょうか。それ自体を否定しているわけではありません。しかしそれは、ものづくりとは違うと思うのです。
もともと帯は西陣、博多、桐生と言われてきました。これには理由があります。西陣はいうまでもなく京都が背景にあります。博多は西国、西の文化が背景にあり、桐生には江戸の文化が背景にあったのです。しかし江戸の文化が明治維新により殆ど崩壊したことで、桐生産地は事実上消滅に近い状態となりました。今もう一度復興させようとしています。しかし、博多の人はそういう危機感を持っていないのではないでしょうか。西陣はずっと在るから、博多もずっと在ったから、これからもずっと在ると思っている。一方、桐生のように江戸時代に三大産地と言われながらも消滅に近い産地があるのです。
友禅でも同じことが言えます。京友禅、加賀友禅、東京友禅と言われていましたが、東京友禅は江戸小紋しか今は思い浮かびません。その復刻に共に取り組んでおりますが、そういう意味で先ほど信喬さんがおっしゃった「博多人形なんて買いたくないでしょ」という言葉は真剣に考えて欲しいと思います。
油断していると、きものなんて買いたくないでしょ、文化なんて面倒くさいでしょ、みんなTシャツにGパン履いて、カップヌードル食べて、コンビニでチンしていればいいじゃない…という世界になっていくのです。
しかしそれは、コンビニでチンしている人が悪いのではありません。「面倒だけど素敵な感動や暮らし方や装い方がある」ということを提案できてない方が悪いのだと思います。
矢嶋: 私も一般的な博多人形には魅力を感じません。しかし信喬さんの人形からは、あるときには勇気、あるときには癒し、あるときには優しさをすごく感じるのです。それは信喬さんが博多人形一般をつくっているのではなく、自分の信喬人形を作っているからなんですね。そういう意味で私はきもの一般や帯一般というのはありえないと思うのです。どのようなきものや帯を創るのか、そしてそれをその地域ごとに深めていかねばなりません。
今日、私は信喬さんが「博多づくし」で来られると思ったので、沖縄・奄美の「琉球づくし」で参りました。
今日着ているきものは、大島紬の源流となった久米島紬です。帯は、3度も死滅し、そこから立ち直った紅型の帯、羽織は芭蕉染めの大島紬です。久米島と沖縄本島の首里と奄美は、今は鹿児島と沖縄で違う県ですが、これらは元々同じ文化圏に属していました。ところがそういう同じ文化圏に属していたものを着るということを、久米島の人も、首里の人も、奄美の人も気づいていないのです。
矢嶋: 私はなにも同じ所だからいいというわけではなく、こういうことに気づくことも文化だと思うのです。自分がいる場所がどういう所か、ということを深めていくことがグローバルに通用するローカル、あるいは文明に通用する文化、もっと言えばグローバルになっても通用する自分というものの居場所を見つけることになるのではないかと思います。人間というのは最終的には究極のローカル(1人しかいない)です。自分の周辺にある生まれた場所、今自分がしている仕事、自分が関わっている周辺社会、これらを徹底的に掘り下げていくことの中からしか日本のものづくりというのは出来ないと思います。
今締めている帯は15代目が作った城間紅型の帯ですが、紅型というのは明治政府の琉球処分により琉球王朝が廃絶され、戦争で20万人が殺され、焼き尽くされて、さらに27年間にわたって占領され米軍の文化の中に置かれる という3回の危機から立ち直ってきたものです。ところが紅型の展示会に私どもの社員が行くと、すぐ目に見えるものを見ようとします。どういう技術・手法で創られたのですか、顔料ですか染料ですか、型紙は何枚ですか…つまり目に見えたものしか見ないのです。また、14代目の城間栄喜さんがこう言いました、15代目の城間栄順さんは…、16代目の城間栄市さんはこう言っています… それを一所懸命メモするのです。それを全て否定しませんが、その目に見えるものを見、耳に聞こえるものを聞いているだけでは、それをつくった人、つくろうとしている人の心・気持ち、それを沖縄の言葉を使えば“うむい”と言いますが、その“うむい”(想い)がわからないと思うのです。
ですから日本のものづくりということを考えるとき、自分のルーツを探り、自分の仕事のルーツを深めて、どういう想い、どういう“うむい”でモノをつくっているのか、つくっていくのかということを突き詰めてもらいたい、と思います。

株式会社やまと 会長 矢嶋孝敏

人形作家 中村信喬氏
中村: 今日のきもの姿の説明をさせていただきます。矢嶋会長が「沖縄づくし」でいらっしゃると思ったので、 私は「博多づくし」で来ようと思いました。
これは岡野の羽織、きものは西村の風通織です。またこの帯は人間国宝の小川規三郎先生の帯で、賞をとったときのお祝いに頂いたものです。薄紫に様々な色が入っており、素晴らしい色合いなのが気に入っています。ただ残念なことに、この羽織紐だけは京都です。かつて遙か昔、承天寺の装束を創っていた満田弥三右衛門という博多織の祖がいるのですが、当時の資料によるとお坊さまの衣装や紐などを作ったとあり、更に紐を織る機もあったそうなので、是非復元してほしいと、この博多織デベロップメントカレッジが開校した際から言っておりました。その復元が出来ていれば、これも博多で手に入れることができたのですが残念です。是非そこまでのことをして欲しいと思います。
さて、日本のものづくりに話を戻します。
私は全国の山鉾連合会の修復保存技術者を務めています。富山の城端祭りや犬山、そして八代の妙見祭などに顔を出し、400年前からあるような人形の修復作業に関わっています。こうした仕事をしていますと、日本のものづくりが危機的な状況にあることが感じられます。お祭りの山車の人形は何百年も続いています。博多の場合は、無形文化財ですのでお祭りの行事自体が文化財です。よそでは山車などそのものが有形文化財となっています。代々にわたり人形を創り、関わっている所が、初めと終わりで言っていることが全く変わってしまう伝言ゲームのように初代とその後の数代を経ると、とんでもないことになって修復や復元を行なっているのを目のあたりにします。それは破壊としか言いようがありません。
京都はその名前ゆえにパリと同じで、ものづくりという工人が市内には殆どおりません。周辺部の人たちで成り立っており、京都自体はプロデュースの街となっています。私も京都での修行時代、京都にはすごい人が大勢いましたから、京都は優れていると言っていますが、今では端から見ると、京都が日本の最高峰と思っているがゆえに危機的な状況にあることが伺えます。今はまだ少数ながら優れた人たちがいるので良いですが、そういう技術の人がいなくなってしまったら、そこから復元するのに何十年も掛かりますし、もとの100%レベルとはいきません。生きている人が教えるとほぼ100%出来ます。大体30年が一代とすれば、20年周期で御遷宮する時のように教えることはできるのです。しかし、人が途絶え、後に研究者が出てきて、復興に20~30年掛かったとしても、80%くらいにしかなりません。たった一人が生きている、城間さんの所もそうですが、口で言って尚且つして見せて教えていくと、ほぼそれに近い形、もしくはその人が努力すればその先代を超えるものをつくれるかもしれません。
日本のものづくりは細分化されており、雨後の筍のように伝統に携わる仕事をやりたい、という若い人も増えています。しかし全てが良いものではありません。本当に良いものを選ぶ側、手に取る側がいて、尚且つお足(お代金)を払っていただいて身につけてもらい使ってもらえるもの、これはとんでもなく凄いことだと思います。そのレベルになれるかどうか。うちの息子の人形も、たまに売れます。しかし、たまにでは生活できません。本当のプロというのは、何ヵ月も何年も家族を養ってはじめて本当のものづくりとなるわけです。ですから若い人には、そうなれるよう努力してもらいたいし、また、そういう人のものを買って欲しいと思います。でもそれは決して高いものではありません。

中村: 矢嶋会長の書籍「きものの森」に、ミントグリーンのレースのきものがありました。私は何十万もするのだろうと思っておりましたが、6万8千円で買えるそうです。本当に良いものが若い人たちでも着られる、しかも洒落た色で。ハイヒールを履いてもかっこいい。これが本当のものづくりだなぁと私は思いました。これが世界で戦えるものだと。本当の日本のものづくりというのは、こういうことを目指さないといけないのだと思いました。
終りに
矢嶋: 皆さんに感じてもらいたいのは、博多という産地も、人形という文化も、きものという文化も「在るものではなく創るもの」ということです。創ることをやめた瞬間になくなるのです。そのことを真剣に捉えていかないと、文化に携わる人、あるいは文化を受け継ぐ人はできません。私は、京友禅や西陣が駄目だと言っているわけではありませんが、このままでは駄目になると思うのです。確かに京友禅や西陣は日本全国の頂点的な技術を持っています。しかしそれが、ある意味でマイナスになっていると思うのです。博多も同じかもしれません。なぜかというと「どう創るか、ということばかりに頭がいっている」からです。どう創るか(スキル)は大事です。しかし、もっと大事なことは「何を創るか」です。何を創るか、が無くて、どう創るか、ばかり考えても仕方ありません。本屋にならんでいるノウハウ本、買って読んだときはいいかもしれませんが半年したら捨てられます。ノウハウばかりを追求するのではなく、何を創りたいのか?ということを真剣に問い詰めてもらいたいと思います。
産地も文化も「在るものではなく創るもの」ですが、幸い博多には、あるいは日本には、こうした人形があり、陶器や磁器、織物や染物、きものや帯があり、文化がまだ在るのです。まだ在ることをどう考えるか。よくコップの中に水が“半分も”入っていると思うか“半分しか”入っていないと思うか、今ちょうどその分岐点に立っているのだと思います。「いつまでもあると思うな親とカネ」「いつまでもあると思うな産地と文化」。自分の力で文化を護り育てていこうと思う人、あるいはそれを支援しようと思う人、あるいはその文化をつくることはできなくても大切に護っていこうとする人たちが、一人でも多く増えてくることが、日本のものづくりを支えるのだと私は思います。
中村: つくる側の人は本物を目指して欲しい、購入する側の方は本物をちゃんとセレクトし、応援して欲しい。そうして本物というものが育っていくのだと思います。先ほど楽屋で化学染料と天然染料では色合いが違うという話をしました。天然染料の方が面倒くさいし大変です。すぐにいい色は出ません。やはり面倒くさいことが非常に大事だと思うのです。若い作家をみると、コンピューターでパッと写真を貼ったり、資料でも携帯電話でこれですなどという人もいます。私もスマホやパソコンを使いますが、絵を手で描くということを必ずします。
面倒くさいことをやると、そのものにどれだけ力をかけたのかが乗り移るような気がするのです。簡単にできたものは、どんなに複雑に見せても、やはり簡単にしか乗っていません。絵心がない人でも、ものを作らない人でも、人間というものは感じ、受けとることができるらしいです。本当に面倒くさいことをずっとやり続け、これでもかということをやった時に人が真似できないこととなり、そこに人は憧れるのです。現代アートは、ゴミをアートにしたというのが段々と多くなってきてしまい今はそのようなアート自体が沈静化して来ています。誰にでもできることはアートにもなるかもしれませんけど、本当に優れたものではないと私は思います。 モネの絵などは、当然デッサン自体もすごいですが、そこにはものすごく手間暇かけていて、やはり描けない(真似出来ない)のです。だからより近くで見たいと思うし、そこに人間は引きずり込まれるのだと思います。陶芸であろうが、きものであろうが、草履だろうがなんでも同じだと思います。手間暇かけた美味しい食べ物も同様です。そうした本物を見せていく、創っていく、そこに引き込める力が大事だと思います。
若い人は特に、その力はなんだろうと悩んで欲しい。悩むと何かしたくなります。本を読んだり、山にいったり、川にいったり、掃除してみたり。何が欠けているのかなと思ったりと興味を持つことが本当のものづくりにつながります。また購入する側の方には、もっと良いものはないかな?と探し、そして応援していただきたい。それが日本のものづくりをどんどん良いものにしていくのではないかと思います。
質疑応答
質問: 我々生産者は、値段・プライスの話でいつも頭を悩ませます。果たして自分のつくっているものが絹で、手織りでつくっているのだけど、この値段・値付けで良いのかということをどうしても考えざるを得ません。プライスについてどのように考えれば良いかアドバイスいただきたくお願いします。
矢嶋: 値段というのは誰がつけると思いますか? 創る人がつけるものではありません。小売屋が決めるものでもありません。値段はお客様が決めるものです。だからお客様にとって、どういう値段でなければいけないかということを考えていかなければなりません。絹である、手織りであるということは、価値の条件の一つであっても、それがすなわち価値ではありません。有機栽培でつくった農作物があるとします。それは有機栽培であることで、ある種、価値はあるけれど、それが美味しくなければ誰も買おうとはしません。有機栽培であること自体、手織りであること自体に、必ずしも価値があるわけではないのです。相手に認めてもらえる価値かどうかが重要なのです。
きものや帯を飾り物ではなく着てもらおうと思うならば、洋服の値段ともっと比べることが必要です。絹は材質からして高い。しかし、レースのきものであれば6万8千円で出来ます。ウールのきものならオーダーメイドで4万9千円。コットンのきものは3万9千円。そういう価格のあり方を勉強した上で、絹は何故高いのかと言えば、絹は天然繊維であり、材質がバラバラであり、そして蚕がはきだす第二の皮膚であるからこそ人間の皮膚に一番近く、だからこそ手入れも面倒だ、という性質があるからです。
一方、経済産業省の去年のきものアンケートでは、きもので買いたいと思う値段には2つのヤマがあり、それは5万円と10万円でした。絹ではなかなか難しい。となれば洗えるポリエステルや綿・ウール等で良いのです。では絹は高くても良いかというと、それでは価格の階段がばらけてしまいます。5万円以下は綿、10万円以下はウールとするなら、絹のきものは15万なのか、20万なのか。その辺を洋服での価格の階段を勉強し、自分が決める値段ではなくて、商品として流通する値段というものをもっと研究したらいかがかなと思います。
中村: 研修生の方はまだ社会に出ていないので、糸代と染料代、そこにちょっとだけ足した値段にするべきだと思います。父が倒れたときに最初につくったものは、最低限の材料代になればいいと思って値段をつけました。息子が芸大でコンテストに出品した折、価格を付けなければならないので、私が材料代だけつけなさい、と言ったところ、グランプリを獲ったことで、教授から安すぎるから値段を上げましょうと言われたそうです。モノは人が価格を決めてくれるのだと息子は少し分かってくれたと思います。
私も還暦近くになってきて、業界の中で今、一番高い値がついているのですが、それは自分がずっと吊り上げてきたわけではありません。もし吊り上げているとすれば、それは虚構のバブルになってしまいます。それは本当の価値ではなく、バブルのブランドです。それはどこかで自分を苦しめるし、破綻が起きてしまいます。
だから、学生なら、めちゃくちゃ安くつけたらいいと思います。それこそ、こんな値段つけて大丈夫というくらい安く。そのなかで、相手の方が値を上げてくれることもありますし、逆に、それでも買われなければその値段でもいらないというように捉える、それでいいのだと思います。
質問: 私は博多人形が好きです。新聞記者の方にも、きものではなく、常々人形の方をとりあげられてしまいますが、やっぱり「きもの」は分かりにくいのかなぁと思っています。織物・帯の魅力というものを十分に伝えきれていない、生活習慣からも離れているというのが、そもそも仕方のないことかなと思うのです。私には子供がいるので、子供を通じて伝えられたら…と思っています。やはり子供のころから慣れ親しむ、子供のころから知っているというだけで全然違うと思いますので、子供達に対してどういうことをやっていくことが文化を残すということになるのかについてお伺いしたく思います。
中村: 人形というのは人の形です。人をずっと見ています。人形というのはやはり身近なものなのですね。わかりやすいのだと思います。だからすっと入ってくる。ちょうど昨日、書ときものの反物を審査する機会がありました。書は縦にすっと目に入ってきたのに対し、反物は横に寝かされていてわかりにくいですよね。クオリティ高く、すごい技術で織ってあるのですが、そういう差はあると思います。
また、私は物心ついたころから粘土を触ってきていますから、大学を卒業して新たにこの世界に入ってきた人たちとは全く違いました。生まれた時からそういう環境にいることが関係しているのだと思います。
やはりその環境というのは大事で、どんなものでもいいから子供達に本物を見せていく。私が京都で修行していたときに、目垢がつくという言葉がありましたが、目垢がつくようなものを見せてはいけない。子供には良い言葉を使い、良いものを見せていくことがベストだと思っています。
矢嶋: 子供が10歳の時に、きものを着たいと言いました。私が着ていた片貝木綿のきものと同じ柄できものを作りました。もちろん帯は締められないから兵児帯です。決して高いものではなく、そういうところから実際にきものを着るという“体験”をさせてあげることが大切だと思います。
また、絹の高いフォーマルきものは日常から離れつつありますが、ゆかたは今みんな着ますよね。10年くらい前、なぜ綿のゆかたにポリエステルの帯しか合わせないのだろうと思い、ゆかたに博多紗献上の帯を合わせれば、と気づきました。今では日本全国のゆかたにコーディネートされ、若い人がその博多紗献上の絹の帯を締めています。フォーマルの綴れの帯や、佐賀錦といった帯は若い人にとって高くて買えないけど、博多紗献上の帯だったら買えるのですね。
つまり “体験”させること=文化に触れることになるのです。こうした入り口を作ってあげることが、とても大切だと思います。承天寺の住職とお茶の話をしたとき、静岡ですら子供がお茶を飲まない、という話がありました。お茶は飲んでいるけれど、それはペットボトルのお茶。さらに家には急須がない。どうするか?住職と話したのは、給食のときに急須に入れてお茶を出す当番を決め、みんなでお茶の入れっこをしたらどうかということでした。そうすると、誰々くんは乱暴なのにお茶は美味いとか、誰々ちゃんは可愛いけど、お茶のいれかたが下手だとか、そんなふうに人によってお茶の味は違うということがわかるのです。褒められた誰々くんは家に帰って喜んでお茶をいれるし、下手だといわれた子は悔しがって同じく家に帰ってお茶をいれる。そうすると「お母さん、何でうちには急須がないの?」となります。そうすると親は慌てて急須を買いにいくわけです。そういう形で文化というのは、子供のうちから体験させることで受け継がれていくと思いますので、大人は、自分からそれを言えない子供にそれを体験させる義務があるのだと私は思います。
司会:これで「グローバル社会における日本のものづくり」について、矢嶋孝敏会長、中村信喬先生の特別対談を終了させて頂きます。本日は長時間にわたりご静聴ありがとうございました。
中村 信喬(なかむら しんきょう)
人形作家
日本工芸会理事 西部支部副幹事長
1957年福岡県福岡市生まれ、1979年九州産業大学芸術学部美術学科卒業、1985年に伝統工芸人形展初入選後、伝統工芸人形展;文化庁長官賞、日本伝統工芸展;高松宮記念賞、福岡県文化賞創造部門受賞、伝統文化ポーラ賞;優秀賞など受賞多数。2011年ローマ法王に謁見、伊東マンショ像を献上。日本工芸会理事、同人形部副幹事長、同西部支部副幹事長、九州産業大学芸術学部非常勤講師、博多織デベロップメントカレッジ講師
矢嶋 孝敏(やじま たかとし)
株式会社やまと 代表取締役会長
1950年東京都新宿区生まれ、1972年早稲田大学政治経済学部卒業、1988年株式会社やまと代表取締役社長就任、2010年同社代表取締役会長就任。アパレルのトップスタイリスト大森伃佑子氏ディレクションによる「DOUBLE MAISON」をはじめ「なでしこ」「Y. & SONS」「THE YARD」など、数多くのブランドや店舗を手がけている。2015年 書籍『きものの森』出版。一般財団法人「衣服研究振興会」理事長