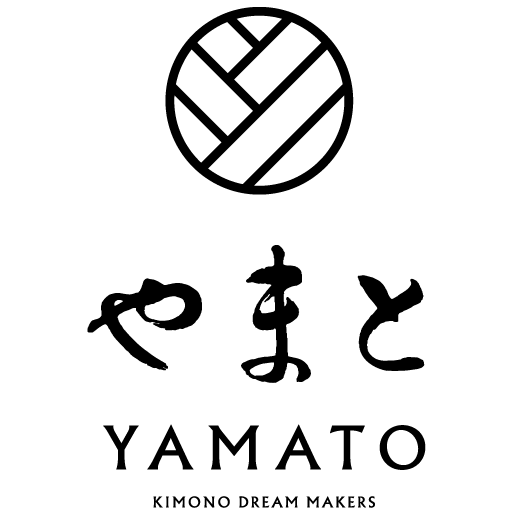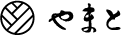DOUBLE MAISON 神楽坂店 オープン記念対談

ブランドスタートから7年越しで念願のリアルショップがオープンしましたが、今どういうお気持ちでしょうか。

大森:想いは溢れるほどあって・・・語りつくせないです。7年越し、と言いましたが、私としては8年なんです。準備期間が都合1年あって、いろんなことで試行錯誤をして、それからメゾンがスタートしたので。
そもそものきっかけは、私がきもののお仕事をやっている中でいろんなクエスチョンがあって、「もうちょっとこうしたらもっと良いのに」っていうことがすごく多かったんです。お洋服だとあまり思わなかったことが、きものだとクエスチョンになる。私は女子の仕事をもう30年やってきているので、その違いがだいぶわかるような仕事の仕方もしてきたんじゃないかってところでメゾンを始めたわけなんですけれども、そこがなかなか深い森でしたね。お店を出すのに8年かかったくらいですから。
深い森、というのは?
大森:深い森で、いろんなものに遭遇するんですよ。可愛い子リスとか、珍獣とか(笑)。それと、道にも迷います。 こっちでよかったはずなのにどうもこっちじゃないとか、磁石が狂うみたいな、すんなりいくはずがそうもいかないんだ、ということがきものの世界では起きるんです。 やはり男性の頭でつくられたことが強くって、女子が普通に「これでいいんじゃないか」とか「あ、可愛い!」っていうような小さな驚きの積み重ねではないエリアなんだな、と未だに思います。
きものの壁、男の壁、会社の壁、と言うべきものでしょうね。
大森:そう、会社の壁。黒田さんも私も一匹狼的フリーで、横の繋がりでやってきました。でも会社は明らかなルールがあって、個人判断ではなく、やっぱり縦なんだなあと思います。
リアルショップの地に神楽坂を選ばれたのは何故ですか?
大森:始めから言っていた条件は「ファッションエリアじゃない所」でした。原宿や表参道、中目黒、代官山じゃない、だとしたら何処だろうっていう消去法で神楽坂や代々木上原が残って、神楽坂の来れば来るほどの魅力に「ここがいい!」ってなりました。
神楽坂は東京の真ん中なのにこのレベルの商店街があって、いろんな年代の人がいて。ファッションエリアじゃない人たちがいる、というのは私にとってリアルで新鮮で、わざわざ行ってみる価値があるというか。人はちゃんと来ていただける場所だと思うんです。
黒田:メインストリームではないということですよね。サブカルチャーという言い方は少し違うかもしれませんが、ファッションだけじゃない部分が面白さを持っていて、服だけを目的にしないでもいい。そういう意味では違う風が吹きやすいのかなと。
大森:今はそうだと思うんです。80年代の頃は、ファッションだったら本当にファッションだけっていうペンタゴングラフがとんがった生活をしている若者がいっぱいいましたが、 今は休日も充実しているし恋愛もするし、食にも興味があり仕事もまあする。その中ではお洒落もそこそこな感じかもしれない。そのバランスの違いですよね。
神楽坂は「何々系」みたいにひとつに特化していない街で、飲食店もあれば買い物もできるし、古い神社もあります。
草場店長はこの神楽坂という街に出逢ってみて、いかがですか。

草場:神楽坂にはほとんど来たことがなかったのですが、来るたびに面白いなって感じる街はそうそう無いと思います。 普通は買い物とか目的ありきで出かけますが、神楽坂は毎回新しい発見があるので、用事が無くても何となくお散歩したくなるんです。 オープンの前には何回も来ましたし、もっと神楽坂を知りたいので今からも楽しみです。
黒田さんはショップの総合ディレクションを手がけられたわけですが、最初にこのお店の原型を見てどう思われましたか。

黒田:このエリアは元々印刷工場が多く、昔は活版屋さんもあったんですよ。若い頃から来ていて知っていたのもあって、ある程度の規模というか建物の尺は予想がつきました。 実際に物件を見たのは3月末なんですが、スケール感は自分のイメージとそんなに違いませんでしたね。ただ築60年超えと建ってからあまりにも時間が経っていたので、建物として大丈夫かなと(笑)。 でもこの物件のお隣のアイダアトリエさん(一級建築士事務所)が設計されていたので、その点に関しては安心していました。
築66年の印刷工場という場で大森さんの想いを実現するのに、どういう風に考えられましたか。
黒田:自分が全て建築・設計をしたわけではなくそれぞれの専門家がいらっしゃったのですが、僕の仕事はまず大森さんとのイメージの共有でした。 大森さんと話す中で、ある映画のイメージとか納屋みたいなものとか、そういうものがすぐ出てきてわりと早い段階で共有できていたので、それを現実にどうやるかを工程の中で考えていく、といった流れで進んでいきました。
大森:元々黒田さんとはお仕事をしていますし、彼の世界観はわかったうえでだったので、入り方は無理がなかったと思います。
先ほどお話にあがった「ある映画」とは?
大森:ナスターシャ・キンスキー主演の「テス」(仏・英1979年)です。
黒田:ロマン・ポランスキー監督の作品で、当時は紅茶か何かのCMでそのイメージを使われていたような覚えがあります。
大森:ナスターシャ・キンスキーはほんっっとうに可愛い人で、彼女が80年代にan・anでKENZOのファッションフォトをやっていたのは忘れもしません。 いわゆるファンタジーなファッションの頃にモデルさんもされていました。「パリ、テキサス」(西独・仏1984年)にも出演していましたよね。
黒田:ヴィム・ヴェンダースというドイツ人の監督の作品ですね。男女と家庭の崩壊と融合を描いたロードムービーの傑作です。
大森:黒田さんと私の時代って、ファッションをやる人はここに行くべき、これを着るべき、これを見るべき、これを食べるべき、っていう「べき」が必ずあった気がします。 目印というか。六本木WAVEには行かないといけないとか、夜の遊びはこうしなきゃいけないっていう(笑)。「パリ、テキサス」は当時ファッションを志す人は見るべき映画で、サントラも買うくらいの影響力でした。
黒田:あとは「ベティ・ブルー」(仏・1986年)でしょう。時代のアイコンだったんですね。
おふたりでイメージを共有して実際にお店づくりをしていく中で、苦労したことがあれば教えてください。

黒田:大森さんは家具や空間そのものの質感を一番気にしていたのですが、元が日本家屋なので、どうしても和の尺になってしまうんです。 こちらが何か手を加えたとしても、何となく日本家屋の方に引っ張られてしまうというか。それはそれで良しとして、何処を活かすかというバランスはやりながら考えるしかなかったので、やっぱりそこがリノベーションの難しさだなとは思いました。
大森:そうなんです。実はこのお店は、私がやりたい世界観そのものというわけではないんですよ。日本家屋っていうのと、新築部分があること。什器だとかクーラーだとか配管だとか。
黒田:それはもう新築じゃないとね、昭和時代の中古のクーラーを持ってくるわけにいかないし(笑)。
大森:完璧を求めるのであればそういうことなんですよ(笑)。でもそうはいかなかったから、古い家屋と新しい設備という中でどうバランスを取るか。 それは黒田さんと大重くん(設計デザイナー・菊田工務店)の阿吽でした。全員が同じイメージを共有しているんだけれども、どっちにも引っ張られ過ぎずにバランスを取らないとっていう。
そうした過程を経てこのお店ができたわけですが、店長はまだ改装中の、未完成のお店を見た時にどう感じましたか?
草場:物件が決まってすぐに、その時は外観だけでしたが初めてお店を見て、「始まるんだ」と思いました。 7月に神楽坂でゆかた展をやった時には、中を見させてもらって。着々と進んでいるものの、やっぱり工事段階ではリアルには想像できませんでした。でも竣工式で、真っ白な壁に包まれた空間や窓辺で話している大森さんと黒田さんを見て、 これからの楽しみや不安とか、いろんな気持ちでドキドキしたのを覚えています。家具が入る日までは、本当にここで始まるのかなという気持ちでした。
実際に家具が入り大森さんのディスプレイが始まっていったのを見て、どうでしたか。
草場:家具が無い状態でも他の準備を進めなければならなかったのですが、その状況で何が必要かを想像して動くのがすごく大変でした。 家具が入り少しお店っぽくなった中で作業をしていて感じたのは、大森さんは制限のある中で強い人だなと。 いざ商品だけを並べると空間的に寂しかったり足りない所ってたくさんあって、特に2階のギンガムの部屋はほとんどが非売品の備品だらけなんですよ。 大森さんがディスプレイをしながら指示をされて、必要なものを自分たちでつくってきたので、その間のスピード感というかライブ感はドラマティックでした。クリエイティブってこういうことなんだな、というのを間近で見られました。
大森:私もお店をつくるのは初めてで未経験な部分が多かったので、この箱でできることって何だろう、と想像するのがなかなか難しかったんですよ。 だから今まで私が洋服を撮影するスタジオでやってきた、小物を集めて魅せる場をつくるという考え方にどうしてもなってしまったんです。でもそれはある意味私の強みというか、経験を活かせることだろうと思って。
オープン企画として1階にホワイト、2階にギンガムを選ばれましたよね。


大森:ギンガムは絶対やるべきアイテムで、なんだったらギンガムブランドでいいくらいだと思っています。もうひとつ、私の絶対のマストはクローゼットです。 メゾンの始まりの時から話していますが、女の子のクローゼットには過去や未来、夢、いろんなことが詰まっています。 明日着る洋服だけではなく、いつか着たいと憧れる、10年後かもしれない、ずっと着ないかもしれない、だけど自分の大切なものが洋服を通してそこにある。クローゼットは女の子の象徴だと思います。
クローゼットをひとつの象徴として、空間全体、ショップ全体をスタイリングしたということですか?
大森:そうですね。メゾンはいろんな人に支えられてきたので、ネットワークを大事にしようと思って。 家具なら最初に決めた福岡のkrankさんで、というように、その人たちにちゃんと最後まで支えられてやっていくことにいつか意味があるだろう、といつも考えるんです。 なのでたくさんのお店から、というより決めた所からひとつずつ選んでいきました。そうしてこの箱ができたわけですが、意外と私の最初の絵コンテ通りなんですよ。 もっとできるかなと思ったけれど絵コンテ通りに終わったというのは、私の未熟なところかなとも思います。
黒田さんはできあがったこの空間に対してどう思われましたか。
黒田:空間としてはいろんな条件を満たせているかなと。もちろん変わることもこれからもうちょっと深みをつけていくこともできるので、そういう意味ではニュートラルな部分もきちんと残せました。 伸びしろがあるというか、いろいろと使い勝手のある空間には仕上げられたんじゃないかなと思っています。
大森:私が絵コンテ通りにできたのは、それ以外の部分をちゃんと見てくれる黒田さんと、それらを確実かつリアルに落とし込んでくれる大重くんっていうこの3人のチームワークがあったからです。私はのびのびと好きなことをやらせてもらえました。
今回はリメイクも準備されていましたよね。


大森:他に無い存在、わざわざ足を運ぶ価値のあるお店でありたいという意味では、リメイクや1点ものを扱いたいと思っていたので。 このお店にあるのは、何処でも買えるものとか、買いやすいものとか、言い方に語弊があるんですけど誰でも似合うものではない。けれども行くことに価値があって、そこに何か自分を見つけられれば、ということにおいて、1点ものやリメイクの持つ価値は大きいかなって。
そうした経過を経てお店がオープンしたわけですが、来ていただいたお客様に対して感じたことは?
黒田:自分はお店の完成後は手離れというか、来た方たちのリアクションやどういう想いで見ていただいたかを詳しく知ってはいないのですが、 やはり人が来て初めて成立する空間なので、たくさんの方が来てくれたのはすごく良いことだと思います。 空間というのは不思議なもので、例えばそれまで人が全然来ていない場所と、10人でも20人でも来てそれでいない状態とでは全然違ってくると思うんですよね。ともかくお店としては良いスタートを切れたのかなという気はします。
大森:たくさんの人がお店にいるイメージじゃないんですよ。駅ビルみたいな所でわいわい楽しいっていう感じよりも、1人ずつがゆっくり1つずつ、うわーっと想いながら見てほしい。 その場合お店にいるお客様は一度に多くて3人くらいかなという意味では、いわゆる便利な場所ではない、大通りから外れてちょっと路地に入る場所を探していたんだと思います。 最初はいろんな人が会いに来てくれて違う賑わいがあって嬉しかったのですが、これからは静かな佇まいが似合うお店づくりを心がけたいですね。
草場:先日ドアの前で入るかどうかずっと悩んでいるお客様がいらしたのですが、すごくゆっくりドアを開けて入ってきてくださって。 「ドゥーブルメゾンも、どういうブランドかも知らなかった。ただ若い頃に大森さんがすごく好きで、ずっとアクションも起こさずにいたのだけれど、転職を明日に控えて ふと大森さんの名前でネット検索したら、お店を出したとわかって。 勇気を出して何かを変えたくて来た」とお話しくださいました。ひとしきり話して2階へ上がられて、しばらくして私も上がったら、お客様が奥ですーっと涙を流されていたんです。 「丁寧さが本当に伝わってくる。今こういうお店は無いし、このタイミングで勇気を出して来てみて良かった」と仰ってくださって、私もつられて泣いてしまいました。
大森:それは私も泣いてしまいますね・・・。私がやりたいのはそこなんです。可愛いものをつくるとか、きものや洋服をつくる、それが売れる、というのは、その後結果は必ず付いてくると思っていて、となるとやっぱり掴みなんです。 掴みってじゃあ何だろうと言ったら、一生懸命皆頑張っているんだったら自分も一番先に頑張る、みたいな超ベタな理屈なんですよ。そこがやっぱり男子の頭の中のネットワークにはなかなか無いことで、きもの業界にはそういうことがごっそり抜けていてもったいないなって。 女子が心を動かすっていうのはそんなに難しいことでもないし、すっごく素晴らしいものをつくるばかりでもないんです。
一番女子を感動させられるはずのきものが、売上や効率が前面に出ることによって男子的、会社的になって、女子の感動が失われてしまっているんですね。
大森:それは同じ思考力を持った女子だったら見破るんです。あ、ここは匂いが違うなっていうのを嗅ぎ分けながら生きている。森の中に1個素敵な小箱が置いてあるのを、女子は嗅ぎつけられるんです。 ネットワークだったり女子の持つ感性や勘を使って、そこに辿り着く。そして辿り着いた時の感動がすごく大きくって、そういう自分を褒めてあげられるんですよ。それが自分のステップになっていく。 そういう女子の構造を私は身を以て体験しているから、そこを出せたらなって。もう商売ともきものとも仕事とも関係ないですけれど、私がドゥーブルメゾンを始める時に強く思ったのがここです。
黒田さんは以前、実際にこういうものをつくりあげるには長い時間が必要だと仰っていましたね。
黒田:そうですね。工事の期間とは別に、大森さんの8年間も含まれていると思います。 大森さんの言う「いろんなことを上手にビジネスとしてやってもバレちゃう」というのはすごくあって。逆に今だといろんなものを使って事前情報を得たうえでお店に来る場合が多いんですが、 確かに昔の代官山とか、店も全然無かった時代を考えれば、街が持っている魅力の中に突然変異的に面白い店があったなあと今 思い出しました。 もちろん代官山に限らず神楽坂もですが、店づくりってなんとなく、上手になりすぎちゃうとつまらないのかなというのは多少ありますよね。 ドゥーブルメゾンは少し大人向けのブランドだと思うので、その人たちにはやりすぎない程度が有り難いというか。そういう意味では場所として印象が残るかな。
大森:神楽坂ってそのバランスもありますよね。それに、私はこのお店は未完成だと思っていて。点数で言うと60点いかないくらいで、残りは自分たちでどんどん足していくんです。 黒田さんも言っていた伸びしろですね。この店にはいろんな可能性があるんだなと思ってもらえたら、そのお客様はきっともう1回来てくださる。でも1年後に来てそこがちょっとでもくすんでいたら、もうアウトだと思うんです。 その努力を全員がするべきで、くすまないっていうのがすごく大事だと思っています。
女の子っていろんなことに悩んで、不器用に生きているんですよ。結婚しても子どもを産んでも、ずっと仕事をしていても、ずっと不器用でずっと揺れるんです。それと服とは関係ないかもしれないけれど、そういう揺れる人たちの何か目印になったらいいなと思っています。
今の言葉を聞いて、これからこのお店でどうしていきたいですか?
草場:ここが他のお店と違うなと思ったのが、お客様が何かを想いながらお店や商品をご覧になっているんですね。 そういう人たちがいらっしゃるお店なんですよ。いざオープンして、ディスプレイや商品を評価してくださっているのは感じるのですが、このお店やお客様に対して、スタッフがまだ力不足というのが正直なところです。 大森さんが常々言ってくださるんですが、上辺だけの丁寧って、大森さんはもちろんお客様にも見破られてしまうんですよね。 本当の意味での丁寧を表現するのであれば、ドゥーブルメゾンや今の生き方に対して、スタッフ自身もちゃんと悩みながらがむしゃらにやっていかなきゃいけないんです。 そこがまだ何か足りない気がして、私も含め一番の課題だなと思います。
大森:相応しいスタッフ、というのは確かに難しいんですよ。年齢だって、もう少し人生経験のある人の方がいいかもしれない。 この7年間お店ができなかった理由はスタッフなんです。私に近い人がいいのか、きものを売れる人がいいのか、年齢やキャリアはどういう人がいいのかずっと答えが出なかった。でも草場さんと大山さん(ドゥーブルメゾンMD)に会って、真っ白な人でいいんじゃないかって思ったんです。 私もそうだったように、お客様も同じでいろんなキャリアとかはこれから積んでいけばいいわけで、23歳の大山さんから私の年齢までのお客様がいるとしたら、できるんじゃないかって。
そして難しいとは思いますが、皆が私の年齢まで仕事をやり続けてくれたらいいなって思うんです。彼女たちが私の年齢になった時に、自分は生きていないかもしれない。そう考えた時に、私はそこに1つの未来というものを見た気がしました。 いっぱい足りないことだらけなんですけれど、ああ、こうやって繋いでいく未来が見えるっていいなあと思って、このチームで頑張っていくことに決めました。お客様に愛されて育っていけるお店になりたいなって思います。

ありがとうございました。