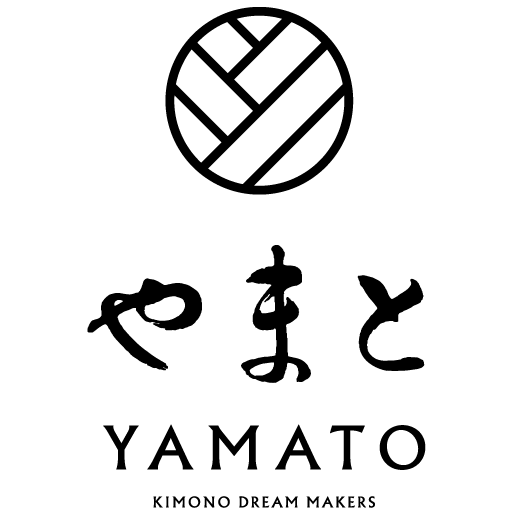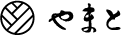誰も知らない加賀友禅 10の秘密

一本の花から無数の図案
矢嶋:一本の花を手に入れて、その花から何十枚もの構図を創り出すと聞きましたが、それはどのようにするのですか?
松島:振り回します。必ず左手で。利き手は右なので、利き手ではない手で花の茎を持ち、360度回るように手首を返して回します。そうすると花が残像として残るんですね。次は逆回し、そして今度は花の下あたりを持って逆さまにして回します。そうすると茎が見え、節があればその見え方も残像となるので、全て頭の中に叩き込みます。それを何度も何度も繰り返し、残像として花をどれだけ覚えていられるか、を練習するのです。

矢嶋:華道池坊次期家元の専好さんが、いけばなの構図をつくるときに教えているやり方と同じですね。友禅作家らしく、左手に持った花にダンスを踊らせて、その残像を頭に刻みつけ、イメージを右手で描く、というのが凄い。
松島:そうです。描くためにわざと左手に持ちます。右手で持ったのでは絶対にイメージが湧きません。描くのが右だから、どうしてもシャットアウトされてしまいます。残像の覚えが悪かったところは繰り返して描く練習をします。
それが終わったら花びらを一枚一枚全部ちぎって並べ、もとの形に組み立てます。しかし絶対に復元ができない。それを自ら身にしみてわからせることで、できる、できないの枠を取り払い、頭で覚えたことを必ず右手で描き出す、ということを自分自身に納得させます。次に花を分解します。茎も切断して切り口を綺麗に全部見て、さらに絵で描いて色を塗ります。解体図のようなものです。さらに裏返して皮を全部取り、それらを綺麗に並べてすべて描いたらまた組み立てます。同じく復元は絶対にできません。
最後に新しい花を持ってきて押し花にし、できあがった押し花をカメラで撮り、実物を見ながら描きます。ここが一番重要です。押し花は平面になるので、私たちが描く図案に近くなるからです。そして押し花の花びらをまたバラバラにして並べていきます。花びらが乾燥した時に反り返ったり、くしゅっと小さくなるのが様々にわかるので、その水分量を自分の頭に入れます。散りかけの花、萎みかけの花、蕾の花、それぞれの水分量を理解することで、描く時の花のふくらみが自然とわかってきます。そうすると今度は花を振り回すだけで描けるようになる。これをしないと絶対に描けません。科学と一緒で、分解・解体しなければいけないのです。
同時に色も見ます。乾燥したときの色の抜け具合や、どれほど抜けるのか、を明記して描きます。ピンクの花も、黄色の花も、青い花も、なり方は違っても、全て茶色になります。それも実際に自ら全部行ったことによって、ようやく追及できた、確信できたひとつです。ただ枯れているから茶色になるのではなく、全てのものは茶色になって終わります。絶対黒にはならない。最後の結末は一緒なんです。人にも死があるように、植物もみな平等に最後の終わりを迎える。それを理解していると、何を描いていても息づいてくると思います。
矢嶋:これも池坊専好さんの話に通じます。華道と友禅が深く繋がっていてびっくりしました。専好さんが外国で花をいけると、展示中にキュレーターが「枯れてきた花や葉を片付けてくれ」と言ってくるのですが、彼女は絶対にそれを拒否します。枯れた花にも美しさがあり、枯れていく様を見せるのが日本の華道の命であるから、と。アレンジメントフラワーとの違いはそこにあり、命の移ろいを感じることが大事だと。
松島:そうですね。自分の中で受ける感情としては同じだと思います。
矢嶋:薔薇にはふたつとして同じ薔薇がない、ともお話しされていましたよね。
松島:同じ薔薇であっても様々な色や種類がありますが、同じ種類の薔薇をたくさん買ってよく見てみると、花びらの付き方も、大きさも、全て違うことに気が付きました。これなら自分のデザインもどんなアイディアが浮かんでもいいのだ、と枠を取り払うことができ、デザインをするのがとても楽になりました。
燈ろう流しの灯篭もつくる

矢嶋:金沢と言えば「加賀友禅燈ろう流し」が有名ですよね。何回か見たことがあるのですが、その灯篭の絵を友禅作家が描いている、という のは実は今日初めて聞きました。
松島:昔はお弟子さんが描いたものですが、そ の起源を辿ると必ず友禅作家が描いていました。友禅作家が描いた灯篭、それを真似て弟子たちが描く、更にそれを小学生が真似て描くという伝統を伝えるべく、多くの団体が灯篭流しの灯篭描きに参加しています。
子育て文化論
矢嶋:灯篭の絵を描くことを通して、友禅作家の技法を弟子や子どもたちに伝えていく、大事な文化継承になるわけですね。どのくらいの数の灯篭を描かれるのですか?
松島:私は一回にひとつしか描きません。灯篭を1200個流すとすると、毎年1200個つくるわけではなく、蝋塗りをして流した後、破損した物に限りつくり直します。翌年分のつくり直しが50個あったとすると、その50個は各工房の先生に振り分けられます。
矢嶋:あの灯篭は使い捨てではなく何回も使うのですね。感動です。
松島:何年かに渡って私がひとつずつ描いたものが、一度に2、3個流れることもあります。それを見つけると「あ、また流れた」、ととても感動を覚えます。ですからなるべく目立つような色で美しく描こう、とする方が多いです。
矢嶋:灯篭に目立つような彩色をして、それに全部蝋をかけるんですか。
松島:はい。その彩色の後、水をはじくために蝋をかけます。
矢嶋:そこは友禅と違うんですね。灯篭流しの灯篭が作家から弟子、小学生にまで伝わっていく技術であると同時に、それが使い捨てではなく何回も何回も直しては使う、ということに改めて感動しました。
小説作家と友禅作家の集中力は同じ
矢嶋:「下町ロケット」や「半沢直樹シリーズ」で著名な小説作家の池井戸潤先生が、松島先生の工房で友禅挿しを体験したそうですね。
松島:どうしても友禅の工房を拝見したいと、前日に突然連絡が入りまして、喜んでお受けしました。友禅挿し体験をする、というお願いはなかったんですが、私たちの方では一応その準備はできていたので、もし宜しければいかがですか、と。そうしたら描いているうちにどんどん吸い込まれるように一所懸命になられていく姿をみて、本当にこの集中力は凄いな、と感じました。
矢嶋:小説作家も友禅作家も集中力が共通する、と実感されたのですね。
松島:はい、見ていてすぐわかりました。描くときのスピードを見ていると、集中しているのでおそらく周りの音がぼやっと聴こえているだけだと思うんです。私もそうで自分の世界に入っているので、言葉は交わしますがただの音として捉えている。そういうお顔をなさっていました。また、こうしたい、という自分の意思をはっきり持たれていました。その横顔や彩色している姿を見て、作家とは、モノをつくるとはこういうことだ、と非常に共鳴しました。
矢嶋:その時松島先生が池井戸先生に、宮崎友禅斎の想い人の話をされたそうですが、どういうお話なのですか?
松島:諸説ありますが、宮崎友禅斎には想い続けた女性がいまして。その想いを告げられないまま、彼女は他人の妻になり、病に倒れます。友禅斎は彼女を元気づけようと一枚のきものを仕立てるのですが、実は仕立て上がるまでに50年かかっています。
矢嶋:ひとりの人を50年愛したと。
松島:出会ってからその方が亡くなるまでの50年です。それも仕立て上がったわけではなく、彩色を終えた時に女性がご病気で倒れたと聞いて、自分の気持ちを伝えるのは今しかないと、きものに渾身の彩色をされた。それが出来上がった当日に危篤の知らせを受け、きものをぎゅっと握りしめたまま女性の家まで走り続けたんですね。でも到着すると同時にその方は息を引きとった。間に合わなかったのです。そして自分のつくったきものを、せめてもと布団の上からかけ、ご家族の了承のもと一緒に燃やしてもらいました。ようやく出来上がったきものを棺に入れて一緒に天国に送る、モノに執着していない友禅斎は凄いと思いました。
矢嶋:モノに対する愛ではなく、無償の愛ですね。
松島:そうです。その女性も、友禅斎の本当の気持ちを知らなかったんです。友禅斎がその方と出会ったのは、植物のスケッチに来ていた犀川のへりでした。彼女は薬草を摘みに来ていて、その時から友禅斎はその方をずっと想い続け、その後人生で色々あったけれどもどうしても忘れられず、きものをつくることにした。その方を想いながら何作も何作も描いたのですが、その方を想うほど納得のいくものができず、その繰り返しで50年が経ったんです。自らの気持ちを整理するために始めた制作活動が、友禅斎がきものをつくる本当のきっかけでした。ですからきものをつくるには、想いなしには絶対にできません。
矢嶋:今の話は一見悲劇のようですが、友禅斎は50年、とても幸せだったかもしれませんね。
世界一細い加賀友禅の糸目の秘密
矢嶋:糊置きをする時に、筒を使いますよね。糊置きの筒は日本中で全部違うんですよ。地域によっては皮や、パティシエの絞り袋のようなものを使うところもあるし、沖縄の紅型の城間先生の工房では、今でも銃弾の先を削って使っています。加賀の糊置きは紅型等と比べるととても細いですよね。あれだけ細い穴をどのように開けるのかを教えてください。そもそも糊置きの先は何で出来ているのですか?
松島:真鍮です。筒先と中筒の二つがあり、先にはめるのを先金と言い、中にはめるのが中筒です。中に油紙で糊を挟み込み、クリップで留めて絞り出します。
矢嶋:パティシエのようにですね。
松島:そうです。これがとてつもなく細いもので、まち針の先が通ってしまう太さだともうアウトです。
矢嶋:凄い!0.何㎜の世界ですね。髪の毛一筋くらいですか?
松島:細い髪の毛だと入るかもしれません。その糊がぎゅっと押し出されるので、どうしても太くなるのですが・・・。
矢嶋:それが他の防染法にない、加賀友禅独特の味わいを出しているのでしょうね。肝心のまち針や普通の髪の毛よりも細い穴をどうやって開けるのですか?

松島:先金は元々穴が開いていません。このボールペンが先金だとすると、ヤスリを少しだけ手首で回しながらアールを取ります。あまり回すとギザギザになってしまい布に傷がつきますので、座布団の上に置いて細心の注意を払いながら行います。
矢嶋:なぜ座布団なのですか。
松島:座布団の生地は主に綿ですので、綿のごつさが丁度いい塩梅なのです。穴を空けるのに二日ほどかかります。
矢嶋:二日もかかるのですか?それは時間にするとどれくらいですか。
松島:食事の合間やテレビを見る時等を使って一日4~5時間、延べ10時間ほどでしょうか。そうして良いアールのついた細い筒が出来上がります。
矢嶋:作家自身が手作りする渾身の10時間ですね。
豆汁を100倍程に薄めて
矢嶋:染めに豆汁を使うのは一般的な知識として知っていましたが、豆汁を100倍程に薄めて使うのは今回初めて知りました。5倍や10倍なら分かりますが、100倍程ともなるとほとんど感じない程の薄さになるのではないですか。
松島:会長がお考えなのは、豆一粒から割り出したものだと思いますが、私の考える100倍程とは、手づかみで30粒ほどの豆をコップにザバッと入れて、5㎝ほどの水に浸します。立派な大豆は水分を吸収するし油分が多いので数は少しでいいのですが、そうでないとたくさん必要です。もちろん立派な大豆を使うのがベースですが、膨らんだ後はその100倍程の水が必要です。
矢嶋:最初のエキスが濃いからですね。それにしても100倍程でも効くとは驚きです。
松島:100倍程でないとダメなんです。そうでなければ生地に薄い線が出て、染める際に染め難が出てしまいます。
矢嶋:今の世の中、何でも濃ければ良いという風潮がありますよね。ビールのアルコール度数も最初3%だったのが、今では4~6%。焼酎も昔は15度だったのが今や20度が一般的で、原酒の43度なんてものもありますが、豆汁は違う。100分の1で100倍の優しさですね。もうひとつは豆汁を100倍程に薄めたもので色を散らす、と仰いましたが、「散らす」という表現について教えてほしいのですが。
松島:100倍程でないとダメなんです。そうでなければ生地に薄い線が出て、染める際に染め難が出てしまいます。
矢嶋:今の世の中、何でも濃ければ良いという風潮がありますよね。ビールのアルコール度数も最初3%だったのが、今では4~6%。焼酎も昔は15度だったのが今や20度が一般的で、原酒の43度なんてものもありますが、豆汁は違う。100分の1で100倍の優しさですね。もうひとつは豆汁を100倍程に薄めたもので色を散らす、と仰いましたが、「散らす」という表現について教えてほしいのですが。
松島:下絵には青花という露草の汁を使うのですが、青花は水で色が散るので、上手に散らすには本当にさらさらの水分が必要です。
矢嶋:そこに入れる100分の1の豆汁の役割は何なのですか?
松島:糊を布に定着させる為です。油分の多い豆汁を使うと綺麗に定着してくれます。
矢嶋:定着剤として必要なんですね。100分の1の優しさで生地を傷めずシミにならず、かつ青花を落としつつ、優しく定着させられる。非常に気を遣いながら、面倒でも優しい工程を経る、加賀友禅の究極の100倍の優しさですね。
「虫食い」10年
矢嶋:虫食いは加賀友禅の大きな特徴のひとつです。池坊専好さんはいけばなの流儀として、枯れた葉をそのままにしておきますが、松島先生は虫食いをいかに美しく表現するのか、そのためにどういう努力をされているのか教えてください。
松島:点粒の点をどれだけ細く一定に描けるかと、色の取り合わせです。色には基色があり、葉の色がグリーンなら虫食いの時はグリーンの明るい色を必ず入れます。上半分の虫を食っているところは、より明るい黄色やピンクを入れます。可愛く綺麗に見せるための色なのですが、それらを繋ぎ合わせるのに点粒が必要です。元々宮崎友禅斎が考え出した虫食いは、虫が歩いて自然にできた模様で、虫が食べている様子を描いたものではありません。
矢嶋:えっ!食べていないのですか。
松島:虫は葉を食べながら歩きますので、食べた後は穴が開くだけですが歩いた後には必ず足跡が付きますし、どこかに汁が付いたりもします。それも模様にしてしまったのが宮崎友禅斎です。
矢嶋:なるほど、虫食いの足跡ですか。
松島:足跡の模様を虫食いに似せて描く、ということです。虫が食うと4つ足や6つ足の足跡や蜜を吸った後の汁が付いていたりして、その汁も乾燥すると点に見えるんですね。それらを頭で想像しながら模様にしていく、それを総合的に「虫食い」と表現します。

矢嶋:想像力を逞しくすれば、一枚の木の葉の上で虫という生物がいて、そこで自分の命を養っている、という表現ですね。
松島:加賀友禅の花に必ず虫食いがあるのは、それで一対と言われているからです。
矢嶋:花や葉は虫を養っているわけですね。講義では虫食い10年と仰っていましたが、それほど難しいということですか?
松島:様々な虫がいるように、虫食いの形も色々なものがあります。虫が上手に葉っぱを食っている様子はミシンで縫ったようになりますが、下手に食えば斑になります。多様な表現をするには、小さな虫、長い虫が食った時のそれぞれの距離等、様々なものを知った上で描かなければなりません。椿の虫食いと芙蓉の虫食いとでは違いますから。
矢嶋:花と同じですね。虫食いは黒を上手く使って描く、とはどういう意味ですか?
松島:黒はシルクブラックという染料がありますが、それを使わずに自分で様々な色を混ぜ合わせ、本当の黒を作ります。シルクブラックは黒ではありますが、薄めるとグレーになる黒なのです。ですから絶対に薄くならない黒を、緑や黄色、赤、青を使って自ら作ります。濃度が必要ですので、それを考慮しながら作っていくのが加賀友禅作家の最大の仕事ではないでしょうか。
出来上がりは鳥が教えてくれる
矢嶋:地染めをする前に糊伏せをしますが、糊は乾くとお煎餅のようになり、口にしても大丈夫だと仰いましたね。つまり加賀友禅は食べても大丈夫なもので染めていると。
松島:伏せ糊は大丈夫ですね。
矢嶋:昔やっていた友禅流しでは、川に浮かぶ糊を鳥が食べに来て、その様子を合図に友禅を引き上げる、と仰いましたが、どういうことでしょうか。
松島:糊の量によっても違いますが、およそ1時間から1時間半でしょうか。糊がふわっと浮いてくる頃合いがあります。それを見計らって鳥達がやってきて、魚も糊を食べ出します。浅野川の染め屋さん達は、鳥が目印だったそうです。
矢嶋:友禅流しの出来上がりは、鳥が教えてくれると。鳥や魚が食べるということは、ゆくゆく人間が食べても大丈夫なのですか?
松島:大丈夫です。糊もですし、それに染料が付着する可能性もありますから、染料もごく自然なものを使用します。証拠として、糊屋さんは必ず舌で味を確かめるんですよ。
矢嶋:友禅流しの出来上がりは、鳥が教えてくれると。鳥や魚が食べるということは、ゆくゆく人間が食べても大丈夫なのですか?
松島:大丈夫です。糊もですし、それに染料が付着する可能性もありますから、染料もごく自然なものを使用します。証拠として、糊屋さんは必ず舌で味を確かめるんですよ。
矢嶋:濃度をですか?
松島:塩気です。その塩で糊が固まるので。濃すぎてもいけないので、その舌で味を感じて濃度を確かめます。私もよく食べています(笑)。
友禅の蒸しに不可欠なのは新聞紙
矢嶋:加賀友禅の蒸しの行程で、布と新聞紙を一枚ずつ交互にかけているのを見た記憶があるのですが、あれは加賀友禅独自の手法ですか?私の知る限りですが、京都や十日町の工房で新聞紙を使っているのをあまり見たことがありません。
松島:加賀友禅の蒸しに新聞紙は不可欠です。布と新聞紙を交互にするのは、布に余計な水分が付着するのを防ぐのと、インクの匂いが虫除けの役割もしてくれるからです。特に梅雨の時期は湿気が凄いので、新聞紙が不可欠なんです。一度使った新聞紙はなるべく使わず、常に新しい新聞紙をかけるようにしています。
矢嶋:昔冷蔵庫がない頃、野菜を新聞紙に包んでいましたよね。一時はなくなりましたが、今も湿気対策にやっている家庭もある。生鮮野菜を包むように、加賀の蒸しにも新聞紙が使われているということですね。
松島:そうですね。一時なくなったのは、恐らくインクに問題があったからです。
矢嶋:一時の新聞は、触ると手にインクがついた記憶があります。その頃ですか?
松島:はい。今はきちんと改善されているので、問題なく使用できます。

矢嶋:他にも松島工房は勉強好きで有名ですよね。作家自身は全工程を分かっているわけですが、お弟子さんははじめはそうじゃない。本来一部のパーツしか担当しないお弟子さんに、全パーツの研修をさせているそうですが、どういう動機で始めて、実際にどうやって教えているのでしょうか。
松島:自分が作家となって分からないことが多くありました。分からないことや不思議なことがこんなにあるのに、どうして私は作家になってしまったんだろう、できないことがたくさんあるのに作家だなんておかしい、と思ったことがきっかけです。まず自分が問屋さんに頼み、悉皆業や色々な専門先を紹介してもらいました。
矢嶋:先生自身が作家としての落款は貰ったけれど、足らないところがあって、問屋さんに行って色んな勉強をさせてもらったわけですね。
松島:自分の知っている方にも頼み込みましたし、染め屋さんとも仲良くなりました。染め屋さんのいろいろな意見を頂戴して、仲良くなっていくうちに、はけの体験などもさせていただきました。そういうことが努力だと思いますし、本来作家はそうあるべきではないかと。彩色だけしていらっしゃる方は、こういう色をこう塗って、と言ってもなぜそうするのかがわかりません。後の工程を知らないから今しなければいけないことが理解できない。前後の工程の気苦労や大変さを知ることで、自分の工程の大切さも改めて分かります。前後に響くことをしている、と意識させるためにも、研修は大切だと思います。
矢嶋:大島紬の研修も同じで、一般的に大島紬は手織りだから大変だと言われますが、その前工程が遥かに大変なんです。前工程の締機で経糸と緯糸の絣柄をつくり、色が吸い込まれてくる。前工程が約6割で、経糸と緯糸が完成すれば高機にかけて織る。もちろん大事な工程ですが、実際には最後の4割なんですよ。一般的な小売は手織りだから凄いですよ、と最後しか見ていない。その前工程の重要性を社員に理解させるのが、一番大事ですよね。
松島:一緒ですね。やはり全部の工程を知ってこそ分かることで、私の工房では生地を織るところから見せていただきたく、また頼み込んで研修に行ってまいりました。
矢嶋:他にも芭蕉布や宮古上布は、績みといって糸をつくるところから行います。一般的な絹糸のような、いわゆる完成された基準品を使っているわけじゃない。不均質の不揃いな糸です。その中から適したものだけをとっていく。それはベテランが一日10時間やっても1,000mくらいしかできない。しかもまた不揃いのものがでてきます。それを知らないと、芭蕉布や宮古上布がどうして高いのか、が理解できないんです。
松島:本当にちゃんと使えるところがどれだけ少ないか、をきちんと分かってもらえるかですよね。買う方も売る方も上っ面なことしか教えられていなければ、理解度がとても低いですし、大切にしようという気持ちが少なくなります。大切にしようと思うのは、自分の印象度か、知識性のどちらかが高い時だと思います。
電話3本で話せた商品取引所時代
松島:色々な職業につきましたが、思い出深いのは商品取引所ですね。同時に3本の電話で話すんですよ。左の肩に1台を挟み、目の前に1台を置き、右の肩に1台を挟んで。同時に、しかも別々の内容を話すことができました。数字の符調は片手だけで1から10までの全ての数字を、それも瞬時にパッパッと出しては引っ込める。しかも商品相場ごとに、1時間おきにこれが繰り返されるわけですから、とてもスピード感と緊張感がありました。
矢嶋:そういう体験を経て、加賀友禅作家となったのはどうしてですか。
松島:親から「石川県に引越しをする」と言われ、ついて行ったのが加賀友禅と出会うきっかけになりました。母は昔から絵がとても好きで、40歳の頃に日本画を習い始めたんです。私は当時OLでしたが、日曜日は母が習ってきた日本画を教えてもらっていました。そして二人一緒に展覧会に出品することになり、いきなり二人とも受賞することができました。私自身、友禅作家になろうとは全く思っていなかったのですが、当時加賀友禅が全盛期であったのと、52歳の頃まで深く絵に関わっていた母を私はずっと近くで見ていたので、母から受けた影響はとても大きいと思っています。
矢嶋:日本画から友禅の道に進んだのはどういう経緯ですか。
松島:私が30歳の時に決意しました。きっかけはテレビのコマーシャルです。当時よく「男は40にして立つ」という言葉を聞きましたが、女性はどこで何を決意するのかと考えた時に、当時は「結婚」しか思い浮かばず、でも私もいずれは何かを決意しなければならない時が絶対に訪れる、と思っていました。そして30歳になったときに「30」という響きが20代とは全く違っていて、責任とかこれから先の事を真剣に考えなければ、と考えていた時に、母から「あなたは絶対友禅作家にならないといけないよ」と勧められたのです。私は優柔不断だったので、母は自分が将来を決めてあげればこの子はその道に進む、と考えたのだと思います。母はとても意志の強い人だったので、私はすんなりと受け入れて、自分には才能がないかもしれない、でも絵を描くのはきらいじゃない、とあとは消去法です。その後友禅作家にもなった母の工房は、私がつくりました。
矢嶋:えっ、母さんは友禅作家だったのですか。日本画を習っていたお母様が友禅作家になったのは何故ですか?
松島:当時、職業安定所で友禅作家を募っていました。母はその第一期生です。
「生きる」をテーマに
矢嶋:いかにも金沢らしい話です。日本新工芸展の初入選作の題は、「私のフウを受け止めて」でしたよね。「見たものをそのまま描くのではなく、感じたものを描いている」「自分の心を写したい」「作家の心が生きている」ということについて、もう少し教えていただけますか。
松島:本日の講演のテーマでもある「生きる」、がキーワードでした。自分の人生で「いつ生きてきたのだろう」、と考える日が来ると随分前から思っていたのですが、その時に悔いのないように「自分が生きてきたところはここだ」、と少しでも長い年月そう思えたら良いなと。そのためには地道な努力と継続、これがなくては生きてきたことにはならない。ですから自分が人から言われたことは全て受け入れよう、と考えを改めました。できることだけを抜粋するのではなく、人から言われたことはなるべくしよう、と。
矢嶋:改めて「生きる」について考えると、加賀友禅は柄のほとんどが花や草木であり、虫食いの虫も、そこに流れる風も日差しも全て生きている。それはどうしたら描くことができるのでしょうか。
松島:それをずっと思っているので、最近では草と木を省いて描くことに専念しています。草も木も花も描かず、線だけで表現して感じていただけるように。「ライン」という作品では、スマートフォンの電源を入れた時に走る電波のイメージで描いて受賞させていただきました。
矢嶋:そういえば池坊専好さんは「出生(しゅっしょう)」という言葉をよく使われます。「出生」とは、草木の個性による命の在り方です。水仙という花の個性だけではなく、同じ水仙の花でも、山の谷あいに咲くものもあれば、伊豆の海を見つめる崖に咲くものもあり、それぞれが違います。風の強い所で咲くもの、風のない所で咲くもの、日差しの強い所で咲くもの、一つひとつが全て違う個体であり、そこに心を運んで個体と心を一つにするのがいけばなと言われますが、通じるところがありますね。
松島:水仙は特に感じますね。加賀の方では福井の水仙が特に有名で、私も何度も見に行きました。水仙の館があって、中に入ると水仙の香りが運ばれるように風が送られていて、山あいにも水仙畑があり、季節になると一気に花を咲かせます。でも館の中と水仙畑とでは、水仙の伸び方や色、香りが違います。同じ産地でも同じ顔をしている水仙は少なく、見ただけでどこの水仙か分かるようになったのは、この仕事をしていての大きな収穫だと思っています。
矢嶋:昔ブラザーズフォーが「七つの水仙」を歌っていて、当時はこの歌が好きでしたが、だんだん違和感を持つようになってきました。その水仙に個体の美しさを感じなくなってきたからです。写真の中の水仙のように思えてしまって。これが造花のような水仙であるのに対し、池坊専好さんのいけばなや松島さんの描いた水仙は、自然の日差しと風を受けた生きた水仙のように思えます。
松島:水仙の葉にも柔らかいもの、強いものがあります。私は水仙の産地に行くと必ず球根を買ってきて自分で育てます。ところが栄養の与え方が上手にできないとなかなか思ったように育ちません。それは紫陽花も他の花も皆同じですね。
矢嶋:本日はありがとうございました。